これまでの活動 2009年
2度目の現地合同合宿
 年が明けて,2009年3月1日,春休みを利用して,私たちは再び福岡現地合同合宿を企画しました.福岡市内でおこなわれたシンポジウムでは,私たちが悩み続けていた問題,つまり事件関係者が全員他界してしまった問題を言及することとなりました.
年が明けて,2009年3月1日,春休みを利用して,私たちは再び福岡現地合同合宿を企画しました.福岡市内でおこなわれたシンポジウムでは,私たちが悩み続けていた問題,つまり事件関係者が全員他界してしまった問題を言及することとなりました.暗い顔でシンポジウムに臨んだ私たちでしたが,九州の学生の1人の言葉に顔をあげました.「私たちひとりひとりこそ,福岡事件の『当事者』なのではないか.」この言葉を聞いたとき,私たちの胸をある言葉が去来しました.
 その言葉は,パネルの1つに記されていたワイツゼッカーの言葉でした.
その言葉は,パネルの1つに記されていたワイツゼッカーの言葉でした.「問題は過去を克服することではありません.さようなことできるわけはありません.
後になって過去を変えたり,起こらなかったことにするわけにはまいりません.
しかし,過去に目を閉ざす者は,結局のところ現在にも盲目となります.
非人間的な行為を心に刻もうとしない者は,またそうした危険に陥りやすいのです.」
 福岡事件の「当事者」として,また,「過去に目を向ける者」の1人として,私たちが出た行動は,九州3大学に限られていた「福岡事件の再審運動を支える学生の会」への関東学院の参加,すなわち,全国へとこの環を広げるために,継続的な福岡事件の支援を約束し合いました.
福岡事件の「当事者」として,また,「過去に目を向ける者」の1人として,私たちが出た行動は,九州3大学に限られていた「福岡事件の再審運動を支える学生の会」への関東学院の参加,すなわち,全国へとこの環を広げるために,継続的な福岡事件の支援を約束し合いました. 2度目の合宿では,これまでシュバイツァー寺の集めた署名提出も行いました.初めて経験する署名提出で,特に関東学院の学生は皆緊張している様子でした.ですが,署名の重みを,そしてその署名に込められた「願い」が届くように提出してきました.
2度目の合宿では,これまでシュバイツァー寺の集めた署名提出も行いました.初めて経験する署名提出で,特に関東学院の学生は皆緊張している様子でした.ですが,署名の重みを,そしてその署名に込められた「願い」が届くように提出してきました.2009年キャンペーンへの参加
 6月のキャンペーンは,6月20日の東京では,狭山事件の再審請求人である石川一雄さんと,文筆家の鎌田慧さんをゲストにお迎えし,6月21日の福岡では,志布志事件の冤罪被害者である川畑幸夫さんと,その支援者である武田佐俊さんをお迎えしました.
6月のキャンペーンは,6月20日の東京では,狭山事件の再審請求人である石川一雄さんと,文筆家の鎌田慧さんをゲストにお迎えし,6月21日の福岡では,志布志事件の冤罪被害者である川畑幸夫さんと,その支援者である武田佐俊さんをお迎えしました.狭山事件も志布志事件も,福岡事件と同様に,自白を中心とした証拠採用によって,有罪判決が下された事件です.冤罪被害者の方々から,直接,自白採取の様子をうかがい,驚きを感じました.
 「お前が自白しないと,今度はお前の弟を尋問するぞ」この言葉によって,度重なる強要に屈せず,否認を続けた石川さんも,とうとう狭山事件の犯行を認める虚偽の自白をしてしまったそうです.また,川端さんは,志布志事件で大きく問題となった,「踏み字」を再現していただき,その文字が家族のものではないと知りつつも家族と面会すら許してもらえない取調体制に,苦しんだそうです.
「お前が自白しないと,今度はお前の弟を尋問するぞ」この言葉によって,度重なる強要に屈せず,否認を続けた石川さんも,とうとう狭山事件の犯行を認める虚偽の自白をしてしまったそうです.また,川端さんは,志布志事件で大きく問題となった,「踏み字」を再現していただき,その文字が家族のものではないと知りつつも家族と面会すら許してもらえない取調体制に,苦しんだそうです.狭山事件が起こったのは,福岡事件から20年後の1963年,そして,志布志事件が起こったのは,つい最近の2003年の出来事ですが,ここにもやはり「冤罪の温床」から苦しんでいる方がいることに,驚きとともに悔しさを強く感じました.
しかし,石川さんのお話は,冤罪の苦しみだけにとどまりませんでした.「再審請求をおこないながら,今は英会話を習っているんです.」刑務所から戻ってきたとき,既にご高齢に達していた石川さんの,その生き生きとした言葉に,私たちは勇気をいただきました.この言葉を受けて,「古川家の支援は美談だけど,それで終わらせてはいけない.」とお話しになった鎌田さんの発言もまた,改めて福岡事件の再審支援運動の活力を与えて下さいました.
2年目の学園祭裁判劇の開催―白か黒か?誤判か誤殺か?―
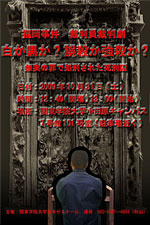 キャンペーンも終わり,また学園祭の季節が近づいてまいりました.私たちは,これまで何度も読みこんできた『真相究明書』をフル活用して,2009年10月31日,関東学院大学の学園祭で裁判劇を企画しました.
キャンペーンも終わり,また学園祭の季節が近づいてまいりました.私たちは,これまで何度も読みこんできた『真相究明書』をフル活用して,2009年10月31日,関東学院大学の学園祭で裁判劇を企画しました.前年にシンポジウムを企画したにもかかわらず,この年は裁判劇として,もう一度『真相究明書』を取り上げました.なぜかというと,福岡事件の問題を理論の問題としてだけではなく,もっと身体的に,もっと「リアル」に感じてみたかったからです.また,この裁判劇は,裁判員裁判としました.裁判員をお招きして,劇を演じることで,これまでの福岡事件裁判を一度白紙に戻し,白紙の状態から,再度福岡事件が白か黒か見極めたかったからです.
 『真相究明書』は,確定有罪判決における各被告人の「証言」や,泰龍氏が西さんや石井さんと個人的におこなった往復書簡等,数々の「叫び」が原文そのままに掲載されています.
『真相究明書』は,確定有罪判決における各被告人の「証言」や,泰龍氏が西さんや石井さんと個人的におこなった往復書簡等,数々の「叫び」が原文そのままに掲載されています.ですが,彼らの切実な「声」を聞いているうちに,罪状事実が検察官によってねつ造されていることに気付いたのです.このねつ造に対し,当時の弁護人は,的確な批判をおこなっていませんでした.このため,私たちの検察側立証批判をそのまま弁護人の主張に置き換えたのです.
 その結果,弁護人の主張は,確定判決後に判明した事実も含んだものとなりました.
その結果,弁護人の主張は,確定判決後に判明した事実も含んだものとなりました.確定判決で証拠採用されたものとして,捜査段階で作製された「自白調書」と,公判での「証言」が挙げられます.
この「自白調書」と公判での「証言」は,正反対のことを話しているのです.裁判劇では,「自白調書」の構成する事実と,「証言」の構成する事実,これら双方の合理性を争う場になりました.検察側は被告人全員に死刑を含めた有罪を求刑し,弁護側は「強盗殺人はねつ造」と無罪を主張しました.
 判決を下す裁判員は,来場者の方にお願いして,登壇していただきました.6人の裁判員は,皆,真剣に,双方の主張する事実を事細かに検証してくださいました.議論が煮詰まってくると,細かな検証を放棄する裁判員が現れ,評議は混乱しました.このことは,福岡事件の検証が非常に忍耐を要するものであることを示しているのかもしれません.
判決を下す裁判員は,来場者の方にお願いして,登壇していただきました.6人の裁判員は,皆,真剣に,双方の主張する事実を事細かに検証してくださいました.議論が煮詰まってくると,細かな検証を放棄する裁判員が現れ,評議は混乱しました.このことは,福岡事件の検証が非常に忍耐を要するものであることを示しているのかもしれません.評議の結果,6名が無罪,3名が有罪に票を入れ,判決では全員が無罪となりました.どちらに転んでもおかしくないと思っておりましたので,この結果は,非常に嬉しいものでした.
copyright (c) 福岡事件学生の会 All rights reserved.